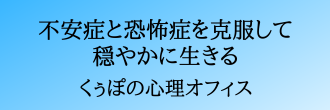不安や恐れという感情は、あなたも経験したことがあると思います。
不安や恐れは本来、何かしらの脅威やストレスに対する正常な反応で、自分を守るための重要な自己防衛機能なのです。
しかし過度な不安や恐れは、自分自身でコントロールできなくなり、日常生活に支障をきたしてしまいます。
その日常生活に支障をきたしている状態を医学的には、不安症や恐怖症と呼ぶのです。
本ページでは、代表的な不安症と恐怖症をご紹介いたします。
下記にご紹介するものは代表的なものですので、ご自身の事例とピッタリ合うものがなければ、お気軽にLINE公式アカウントにてお問い合わせください。
【社交不安症(社交不安障害):SAD(Social Anxiety Disorder)】
以前、社交不安症は対人恐怖症や視線恐怖症、あがり症とも呼ばれていました。
人が集まる場所や注目を浴びる可能性がある状況で、強い不安や恐怖、緊張を感じ、「上手くできなくて恥をかくのではないか?」と考えて、日常生活に支障をきたすほど、人が集まる場所や注目を浴びる可能性がある状況を避けようとするのが社交不安症なのです。
※うつ病やパニック症(パニック障害)を併発する場合もある
また社交不安症は、学童期や思春期の比較的早い年齢で発症することもあり、症状を放置してしまうと不登校や引きこもり、ニートになる可能性が高く、進学や就職、結婚などの大切な場面で問題が表面化するという特徴があります。
【全般不安症(全般性不安障害):GAD(Generalized Anxiety Disorder)】
社交不安症は不安や恐怖の対象が人が集まる場所や注目を浴びる可能性がある状況に限定されていますが、全般不安症は不安や恐れを感じる範囲が非常に広く、日常生活のすべてが対象になります。
そのため不安や恐怖の対象が漠然としているので、それを避けることが難しく、症状が慢性化しやすいという特徴があります。
※うつ病やパニック症(パニック障害)を併発する場合もある
また全般不安症は、本人も周りも「ただ心配性なだけ」と勘違いし対応が遅れ、自宅の外へ出られないなど行動範囲が狭まる傾向にあります。
【パニック症(パニック障害):PD(Panic Disorder)】
パニック症は、何の前触れもなく胸の痛みや動悸、息苦しさ、息切れ、めまい、吐き気などの症状が繰り返し現れます。
そのため「また起きたらどうしよう…」と不安感を持つようになり、症状が起こる可能性のある状況を回避しようとするため、不登校や引きこもり、ニート、働くことができないなどの問題が起こる可能性が非常に高いという特徴があります。
※以前は過呼吸症候群とも呼ばれていました
※うつ病を併発する場合もある
【強迫症(強迫性障害):OCD(Obsessive Compulsive Disorder)】
強迫症は、「手の汚れが気になり洗い続ける」「忘れていないかと気になり何度も確認する」「ミスや失敗などを起こしたのではないかと過剰に不安になる」など、実際には起こりづらいことに囚われ、不合理だと分かっているのに不安を解消するための行動を止めることができません。
また過度な不安を解消するための行動(強迫行動)のため、日常生活に大きな支障をきたす傾向にあります。
※うつ病やパニック症(パニック障害)、全般不安症(全般性不安障害)を併発する場合もある
くぅぽの心理オフィスでは各種カウンセリングを行っておりますが、現在は依頼が殺到し数年待ちとなるため、現在は新規の受付を停止しております。
新規の受付の開始は、『不安症・恐怖症克服!無料メール講座』にてお知らせいたしますので、ご希望の方は下記の無料メール講座にご登録くださいね。
不安症・恐怖症克服!無料メール講座(無料)のご案内ページはこちら!